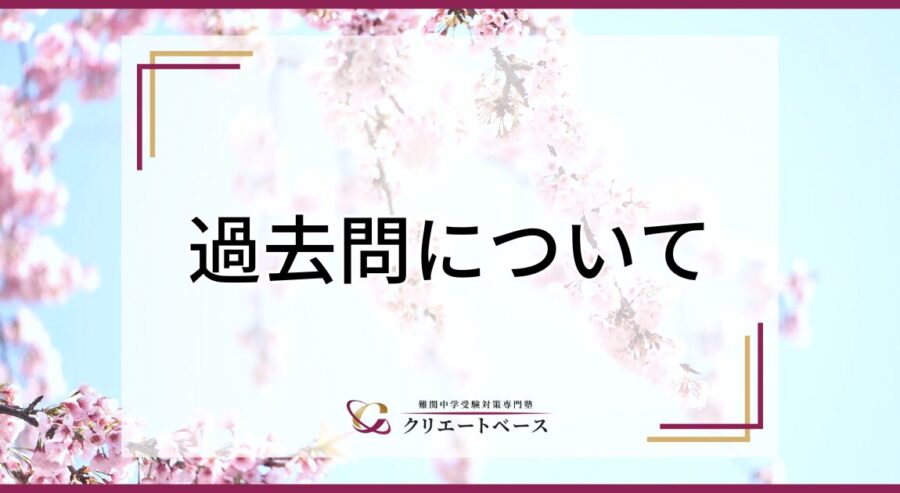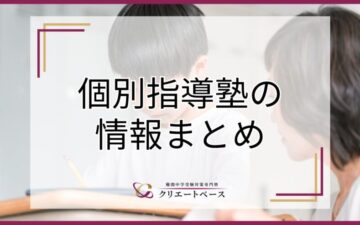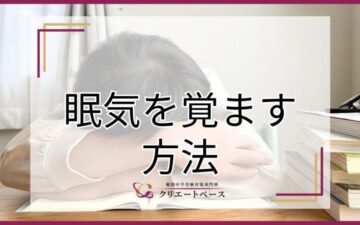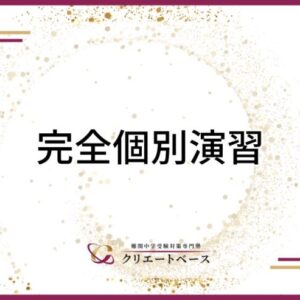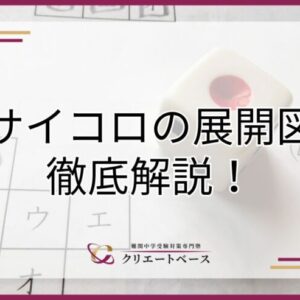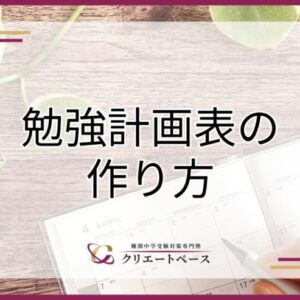「過去問いつから始めたらいいですか?」よくある話です。
一応、見解を述べておきます。
この話題は夏休み前からはじまり、夏休み後そして秋ぐらいに話題になりますね。
10月とかに議論されているのを聞くと、「さっさとやっちゃえば?」と思ったりしてます。
過去問の使用目的としては、大きく分けて以下2つ。
合否の推測
入試直前に、昨年度や一昨年度のものをやってみて、全科目点数を算出し、合格最低点と照らし合わせて、合否を推測してみる手段としての使い方です。
教材として使用
個人的には、過去問は最も質のよい教材であると考えております。
各学校が自校の生徒を選抜するために作られるものであるため、時間をかけて作られていると考えられるからです。
過去問といえど、数十年分ありますので、
たとえば、合否を推測する目的に3年分。教材として使用する目的として、15年分という風に分割すれば、両目的とも満たすことが可能となります。
この辺からざっくりいきます。
そういうことではなくて、教材として使用する場合、「どれぐらいのレベルからやればいいですか?」というお話ですよね。
ここで登場するのが、先日お伝えした「○○√2の法則」です。
「ふざけたこと書きやがって!!」と思われた方。結構真面目に書いてるんですよ・・・
とりあえず、適当に真ん中あたりのものを1年分やってみて、受験者平均点に1/√2(=0.7ぐらい)をかけた得点ぐらいとれているのであれば、そこの過去問をやってもOKだと思っています。
あまりに早い段階でやっても、解法の暗記になってしまいますので、意味がありません。特に、過去問は良質な問題なのでもったいないです。
それなりに得点できるのであれば、取れてたらやってしまうといいかと。どうせ大切においていたところで、間に合わなくなってできなくなります。
「1回やったら覚えてしまうからもったいないよー」
大丈夫です。1回ぐらいやったって、全部覚えいたりしません。
それなら、常時復習テスト満点のはずです。
暗記分野とかはさっさと覚えてもらいましょう。
ただ、一つだけ注意点があるケースが。
記憶力が爆発的にいいお子様。
見たら全部覚えてしまう子。
画像記憶?の類です。
この場合は、上記にあてはまりませんので、注意しないといけません。
志望校順に分けた過去問使用時期の具体例と去年のケースはまた明日。
とりあえず、予告どおり、志望校別順に分けた過去問使用時期の具体例と去年のケースのお話。
まず最初に。関東と国語については、他の先生にお任せします!!
関西では英俊社さんが赤本と呼ばれる過去問集を出しておられます。うちの教室もお取引させていただいており、大変お世話になっております。
で、使うのが「20年本」とか呼ばれる↓

こんなやつ。まあ有名ですよね。
科目的には、国語・算数・理科で、学校別では、灘・甲陽・星光・東大寺・西大和・洛南・洛星とでていますね。なんか足りないような気がするのですが・・・まあいいや
うちの教室が理想としているのは、6年は全部過去問演習です。
現実的なところでいうと、6年生に関しては、
2月ぐらいから算数を開始して、GW明けぐらいから、理科を開始する感じです。
だから、春期で理科のまとめをしているのです・・・
で、去年20年本を全部やろうとしたのですが、全く終わりませんでしたー笑
だって、灘の算数とか甲陽の算数とか1年に2個ずつあるし、洛星さんとか前期とか後期とかあるし、西大和さんに至っては、あっちやこっちやたくさんあります。
のべ180年分ぐらいあります。
3科目だから、540年分とかになります。それの復習もいるから・・・
お・わ・り・ま・せ・ん!!
少し真面目に。
たとえば、去年行ったケースだと、
灘第一志望の場合
算数に関しては、
・5年終わりに灘算数1日目。
・年明けは星光
・GW前後に灘の1日目の復習しながら、洛南やって、
・夏休みぐらいに灘の2日目やって、
・夏休み明けは甲陽と東大寺やって、
・直前に直近3年分やってという感じでした。
理科に関しては、
・5年終わりから星光やって、
・夏休みに甲陽や東大寺や西大和や洛南を同時並行して、
・夏休み明けから灘をやってましたね
・理科は関東の筑駒や開成や麻布とかもやりました。
あまり言うと怒られそうなのですが、学校別の傾向ってあんまり重視してません。
3年分ぐらいやれば慣れると思っているので。
「おまえふざけてんのか?いい加減すぎるだろ?」
まあ真面目です。
色々、お子様の様子をみて微調整はしてますが、
おおまかにはこんな流れかと。
あと、「復習はどうしてんの?」やったらやり直して、
しばらくして、大体3ヶ月ぐらいかな。
時間が空いたときやタイミングがあれば、適当に入れてます。
直前期に総まとめって感じです。
ちゃんとやると案外進まないんですよね・・・
全く参考になりませんね。
ごめんなさい。
以上、過去問を教材として使用する場合のお話でした。
つぎは、過去問を合否の推測に使う場合の基準。
つぎは、合否の推測に使用する場合です。
まず最初に。
合否の予測が完璧にできるわけではありません。当たり前です。
・そもそも母体が違う
・採点基準もわかんない(別ブログで言及予定)
・何なら問題ごとの配点も不明
で、前置きは終了し、とりあえず、パターン分類。
●6年の夏休み以前にやる場合
これに関しては、「教材として使用する場合」に該当します。ただ、この時期に合格最低点あたりをとれてしまってたら・・・
●直前期にやる場合
もうほぼ完成していて当たり前です。直前講習とかやりますが、最近勉強始めたお子様ならいざしらず、何年もやってきて、直前でそんなに成績上がるわけないよねっていうのが個人的見解です。
だったら、合否の推測は100%はできるものの、ほとんどわかるんじゃないの?って話もありますが、上記母体・部分点・採点基準・配点の問題等があるので、結構わかりません。
結局、何もわかんないじゃん!!ってなるのも困りますので、一つだけ目安を。
「これなら、大丈夫って思えるライン」
それは1科目もしくは試験1つ分の点数がなくても、ほぼ合格最低点に届いているケースです。
本番だと余裕で合格するケースですよね。
たとえば、灘なら一番配点が低い国語1日目がなくても合格最低点に届いているケースとか。
より具体的にいうと、80点満点なので、得点が50点なら、合格最低点より50点プラスで合格しているような場合となります。
東大寺だと3科型で「国語はあと漢字だけ取れてれば合格だねー」みたいなケース。
なんか国語ばっかりなくしてますね。ごめんなさい。
これらのケースの場合は、圧倒的に算数が得意で得点力があるケースがほとんどです。
あと、合格採点ラインの得点率が高い場合についてはあまり適用できません。あくまでも、合格得点率が65%以下になってしまう場合に適用できる判断基準であると思われます。
クリエートベースのご案内動画となります。youtubeへ接続されますので、よろしければご覧ください。