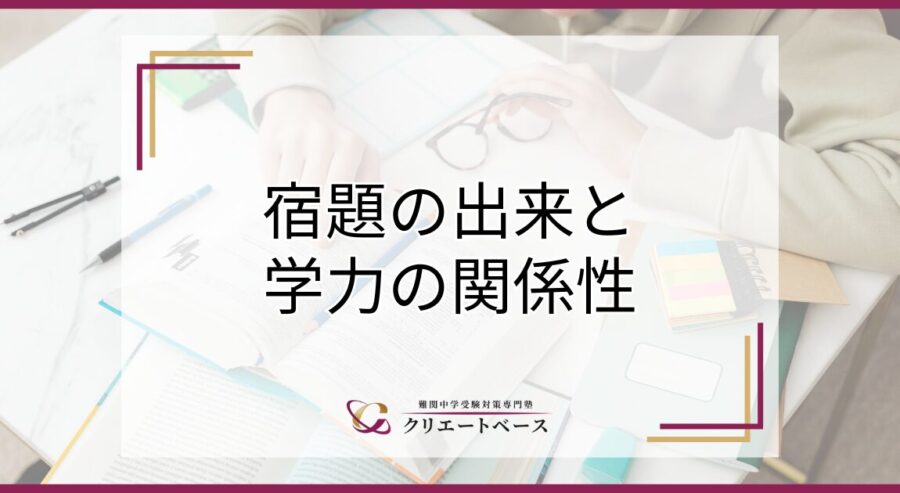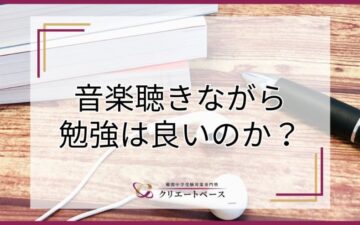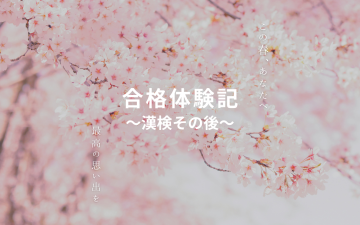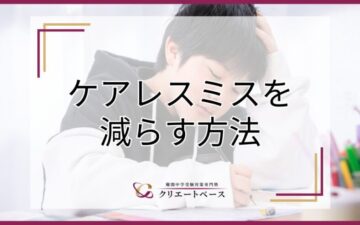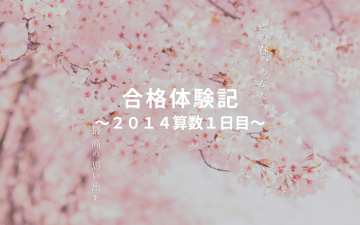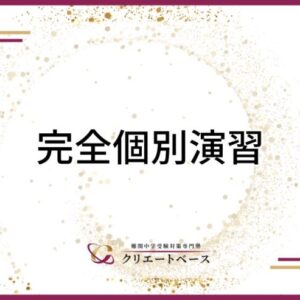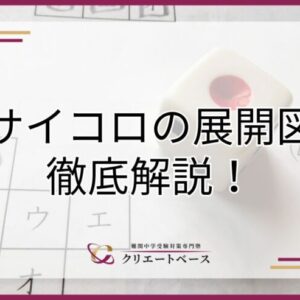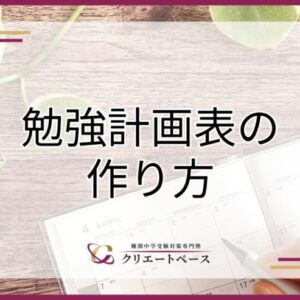宿題はよくですますね。中学受験ではもちろんのこと、大人になってからも出たりします。
小学生や中学生の間は、宿題は学校からであったり、塾からであったり。
そもそも宿題ってどういうつもりで出してるの?っていうのは大切なことです。つまり、その先生がどういう趣旨で宿題を出されているかということから考えいきましょう。
目次
宿題としてのパターン
1 単に復習としての問題
授業したことをの復習としてやってきてねとか、そういう感じのものかと。
2 授業で扱うのに適していない問題
暗記プリントとか漢字とか日記とか、自分でやる割合が多いものです。
3 難問による応用力と思考力の養成のための問題
授業でやったことの理解を深めるために難しい問題を自宅でゆっくり考えながらやってみようねという感じかと。
4 予習としての宿題
これはあまり小学生ではみられないですね。やはり基礎知識がないが故に、一人で勉強することが困難であることが要因でしょう。個人的には、授業の効果を最大化するのは予習だと思っています。
最近では、学校でも塾でも、システム化してしまっているので、上記のようなことはあまり考えられてない面もあるようです。個人的には、期限付きで強制のものでなければ、宿題自体はあるにこしたことはないと思います。だって、嫌ならやらなければいいから。
組織別の宿題の性質
組織の性質上、宿題の趣旨もかわってきます。どちらかというと、ある一定水準の学力をつけることを目的とする学校と学力向上を重視する学習塾といった感じかと。もちろん、最難関中学のように学力向上を重視する学校もありますので、一概に「学校だから」とか「塾だから」という区別ができないのも確かでしょう。
学校の場合
学校の場合は、上記1や2のケースが多いですね。そもそも学力さらには受験勉強が目的の場所ではないので、3のケースに関しては「各自にお任せ」という感じでしょう。
学習塾の場合
学習塾の場合は1から3すべてが含まれているように思われます。特に大手塾に関してはさまざまなクラス帯があるにも関わらず、提供されるテキストは1冊です。テキスト1冊で全クラス帯を網羅しようとすると、レベル別に分けるしかありませんね。たとえば、基本問題・練習問題・応用問題等に分け、「ここのクラスは応用問題は無理して解かなくていいよ」って感じかと。できる子は全部やってねと。さらに、応用問題でも事足りない場合は、さらなる問題集であったり、飛び級であったりということになるのだと思われます。
受験における学校の宿題の位置付け
「宿題が終わらないよー」という嘆き笑は、よく聞きますね。もちろん、終わらない原因として考えられるものは多岐にわたります。宿題が終わらない理由として、一般的に考えられるものを挙げてみます。
・ただの怠慢
これは「終わらない」というのではなく、「やってない」の部類なので省略。
・理解不足
これがしんどいんですよね。ノートみてもわからない。参考書調べてもよくわからん。仕方ないので、解答を写し気味で提出するしかなく・・・みたいな感じになってしまします。
次は、組織別に見てみましょう。
とりあえず、今回は学校の宿題について。塾の宿題が終わらないという件に関しては、量の問題と講座の取捨選択に関わってきます。
小学校の宿題について
受験科目について
中学受験をしようとしている段階で、受験科目について理解力不足でできませんというのは、学力不足かと思われます。結構いらっしゃったりするんです・・・
受験科目以外について
その他の科目、図工や音楽やそんなところでしょう。正直なところ、どんな宿題があるのかもわかってません。こんなところで「適当でいいよね」とかは書けませんので、気が向いたらやる感じでいいんじゃないかなとか思ってます笑
やるかやらないか
やってもそんなに時間はかからないものはやっておいていいのかなと思います。実際に、漢字や社会とかは復習にもなるでしょうし。漢字10回書けとかが嫌なら3回ぐらい適当に書いておけばいいわけで。「やらない」ということで変に担任の先生と争いになり、ストレスを感じるぐらいなら、さっさと適当にやっておけばという感じです。
どうしても無理な場合
ただ、「見るだけで腹が立つ」とか「学校の宿題と聞いただけでうんざりする」いうように、何がなんでもやりたくない場合は、担任の先生に「やりません」と宣言し、断固拒否してみるのもいいかと。実際のところ、直接的に「宿題を強制的にやらせる」というのは不可能なので、絶対にやらなくて済みます。ただ、お子様がご自身で担任の先生と交渉してください。昔に比べて最近は柔軟な対応してくれますので、案外いけたりしそうです。
学校の宿題の役割
とりあえずのところ、中学受験組にとって、小学校の宿題の役割というのは「宿題として出されたものをキッチリと提出期限にまで提出する」という日常生活のルールを学んでいる程度の意味合いのものでしょう。
学校の宿題の管理
そういえば、我が子が行っていた小学校ですが、保護者に宿題の管理させていたような気がします。学校教育においては、「完成させた宿題を提出するかどうか」よりも「宿題を自主的にやったかどうか」の方が大切なような気がします。まあ学校の先生も大変なんでしょう。そういうことにしておきましょう笑
中学校の宿題について
実は、我が子について、学校側から宿題がどれだけだされて、どれだけやっているのか、全く把握していない状況です。中学校以上は勝手にやってくれって感じです。
中学校に関しては、中学受験の対象となる学校とその他に分かれます。中学受験の対象となる中学校については、塾の宿題と同じ関係ですので次回。
公立中学の宿題に関しては、高校受験という観点から考えると、小学校と中学受験の関係と同じですね。なので、上記参照で終了ですね。
まとめ
一言でいうと、好きにしてくださいって感じです。ただ、学校の宿題が処理できないのなら、中学受験はかなり厳しいです。学校の勉強をしっかりしましょう。
「一般的に大手塾の宿題は終わるものではない」ということです。
もちろん、余裕をもって終わる方もいるでしょう。なので、以下のお話へ。
「宿題が終わる」という概念
どういう状態が「宿題が終わった」ことになるのは議論の対象になりますね。
1 とりあえず表面上は欠陥がない状態にする
とりあえず「提出しました」という状態。手段は、答え丸写しとか笑
2 一通りは真面目にやる
とりあえず、一通り解いてみて、間違えた問題は訂正、わからなかったところは答案を参考にするなりして、1度は仕上げた状態をいいます。
3 ほぼ完璧に仕上げる
2の状態からさらに、間違えた部分については、時間をおいてやり直し、最終的にもう1度確認を入れる程度のものです。
今の状態は?
「塾の宿題?そんなもん余裕で終わるよ」って感じの方の多くは、2です。これに対して、我々が要求するレベルというのは3よりさらに上です。間違えた問題に関しては、1ヶ月・3ヶ月等の期間をおいて、やり直し。
極論、できる問題なんてどうでもいいのです。できない問題こそ、成長に必要なわけで。しかし、ある程度学力が上がってしまうと、「できない問題を発見するために、大量のできる問題を解かなければならない」という事態が発生します。
復習テストに向けた宿題処理
復習テストはいい点取りたいし、授業を受けている以上はいい点数を取るべきです。クラス編成にも関係してきますし。ただ、点数を求めるがゆえに、宿題の処理がいい加減になってしまっては本末転倒なのです。
宿題を実質的にきっちりやってきたかというチェックに関しては、表面上は宿題プリント等のチェックOKですが、実質的な理解は、復習テストの点数によって評価されることになります。与えられた期間は1週間。少なくとも3科目あるわけです。それに加え、その他の講座も。キッチリ仕上げるのって、やっぱり無理じゃないですか?
授業というもの
「授業は集中して聞きなさい」。10歳そこそこのお子様に、1時間もしろなんて、まあ無理と思ってます。もちろん、授業を行うにあたり、先生方は「どうしたらお子様たちに伝わるか」等、日々試行錯誤を重ねていらっしゃいます。どれだけ内容が面白くても、どれだけ内容が興味深くても、全員が全員、そして全部が全部を集中して聞くなんて、やっぱり不可能なんだろうなと。だって、集団授業だとさまざまなお子様がいらっしゃるから。
授業の理想的なの受け方
「自分が必要なところだけ集中して聞く」です。少々の無駄は仕方ありません。だって、費用という面で集団授業による恩恵があるから。ただ、どこが「自分にとって必要か」というのがこれまた難しい点ではあります。
まとめ
以下、少々乱暴なまとめ方になります。
授業というものには、どのお子様に対しても多かれ少なかれ「無駄」が発生するものです。
学力の足りているお子様
宿題がサラっとできてしまうケースです。授業で自らが必要なところに集中すればいいと思います。場合によっては、予習してしまってから授業に参加するのもありかと。
学力が不足しているお子様
復習主義を採用している以上、本来想定されているのがこのケースです。授業を聞きながら、ノートをとって、帰宅後、ノートを見返しながら、問題解いて。基本問題はそれなりに解けて、練習問題あたりでつまづき始める感じかと。正直、まあ大変です。
学力が大幅に不足しているお子様
宿題の基本問題的なものからつまづいているケースでは、授業中わけわからなくなり、聞いていないことが多いです。完全に無駄です。