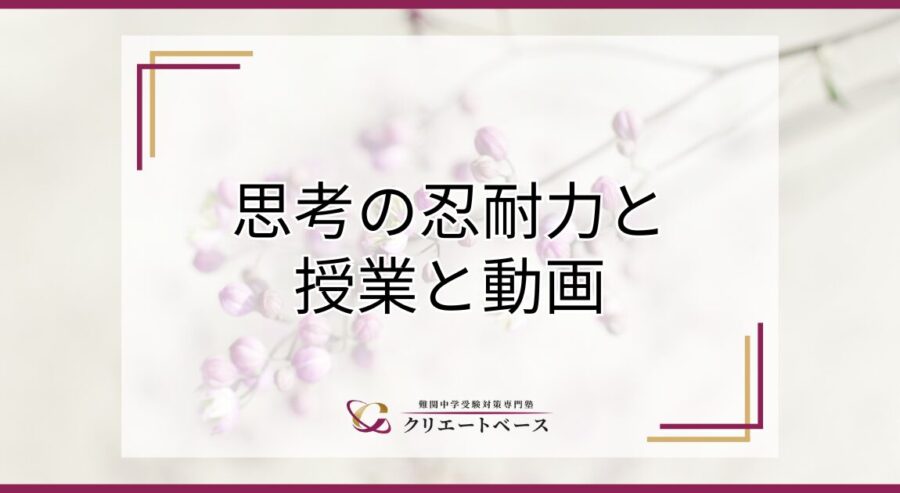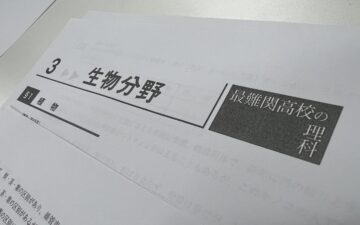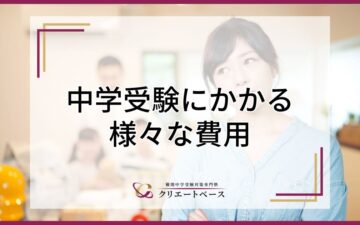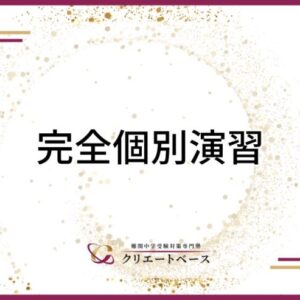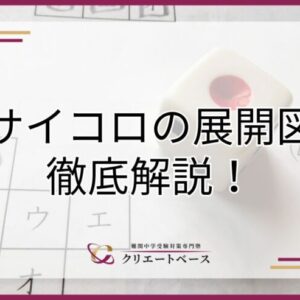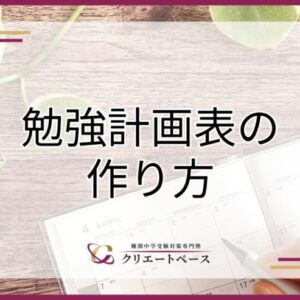思考力は頼り切るのはよくないけど、そこそこ重要という話はよくあるわけで。以前にもそんなことは書いたような気がします。↓ですね。読み返してみて、他人ごとのように「ふーん」と笑ってる自分が謎です笑
目次
よくできるお子様の共通点
見てて思うのは、よく勉強ができるお子様というか、最難関校の過去問とかに取り組んで、そこそこの点数を出してくるお子様は、思考に対する忍耐力があります。
放っておくと、ずっと解いてたりします。そのぐらいやってますね。
今の時期なので、そのレベルの問題をバリバリ時間内で解いて、点数を叩き出してくるということは少ないですが、少なくともやり直しの際、黙々とやってます。
思考のための忍耐力
要するに、脳を使える制限時間の長さでしょうね。スタミナとかともよく似ているのかな。とりあえず、わからないなりに考えていきましょう。短時間集中型と長時間持久型とに分けられそうですよね。
短期集中型
まあ、あの系統の連中です。一瞬で判断する連中。「いつ考えてんねん?」と。実はカラクリがあるのですが、またこれは別の機会に。
長期持久型
決して速さはないけれど、着実に積み上げていく感じでしょうね。
忍耐力はどうやって身につくか
日頃の訓練なんだろうなと思います。常日頃から、脳を使っているかどうか。「寝る子は育つ」っていうのはこの辺から来ているのかな。正確にいうと、「(脳をよく使って、脳を訓練して)育ててる子は、(疲れて)よく寝るものである」といった感じかと。
思考の忍耐力の育成を阻害するもの
TikTokか何かで見たのですが、「1歳半前後のときに動画をみていると脳梗塞状態である」と。他にも「テレビは受動的だから避けた方がいい」というような説はありますよね。
まあ、見てばっかりだしそうなんだろうなと。この状態がつづくと、「脳梗塞」のような状態にもなるのでしょう。起きている時間のほとんどを動画を見ているので、「脳梗塞」と同じような状態みたいなことをおっしゃってましたね。
我が家の子供たちの場合
ところが、ただ異なるケースも身近にあったりするわけで。
実は、うちの子達。テレビもゲームもよくしていたんですよね。「見過ぎやりすぎ」はダメだと思っていたので、時間的な制限はかけていたものの、守るわけもなく。
特に次男くん。問題やらしても、点とりまくるので、ご褒美でゲームしまくり。点数とるから、どしようもない。それでも、めちゃくちゃ考えます。1枚の紙が真っ黒になるぐらい色々書きまくってました。
上記のケースとどう違いがあるんでしょうね。
テレビ等の動画は、思考の忍耐力の育成を阻害するかも?という中で、我が家の子供たちはテレビもゲームも動画も見まくっていたけれども、忍耐力は結構ありましたという流れですね。
おそらく、色々と考えながら、動画を見てたのだと思います。
兄弟そろってで見ていることが多かったせいか、視聴中もそれぞれの見解を述べたり、ツッコミを入れたりしているのです。それこそ、ほぼ黙って見ていることはなかったような・・・頭使ってたんでしょうね。
能動的に利用するということ
以上のことから、テレビ等の動画をみるということが、必ずしも受動的になり、弊害のあるものであるとは限らないということはわかると思います。あくまで能動的か受動的かというのは、主体によって決定されるものであり、いかなるコンテンツであっても、能動的に利用するのであれば、何ら弊害の発生はないものと思われます。
では、これらの話を、中学受験のコンテンツに適用して考えてみましょう。
コンテンツの性質
集団授業の性質
「生徒全員が興味をもって真剣に聞いてくれる授業をしよう」
これは講師全員が理想とするところであり、日々を実現するために努力されていることでしょう。ただ、どうしても生徒が多数になると、レベル差が発生するのです。とあるレベルの子にはピンポイントなものであっても、他の子にとっては退屈なものであったり、ついていけない場合はその場にいるだけのものになったり。
レベル差を原因として、どうしても受動的な部分が発生してしまいますよね。
動画コンテンツの性質
それでは動画による学習はどうでしょう。おそらく、対面で行われる集団授業よりも受動的な面が増えてしまいますよね。それは、目の前に生徒がいないから。コンテンツによっては、集団授業よりも多数を対象としているため、さらにレベル差は広がります。
説教
なんか思いついたので、「説教」とやらも追加しておきます。こんなもの、聞いているわけがありませんね。下手したらただの騒音です。しかも、能動的に説教を利用しようなんてことありません。それなら、はじめから説教されないように行動してますから。
結論
どんなコンテンツであっても、能動的な利用が重要ということです。「頭をつかえ」というのは、「自らが主導権をもって、そのコンテンツを利用する」ということになります。
具体的には、授業中の質問であったり、動画の一時的・巻き戻し・倍速再生等にあらわれるのでしょう。
クリエートベースのご案内動画となります。youtubeへ接続されますので、よろしければご覧ください。