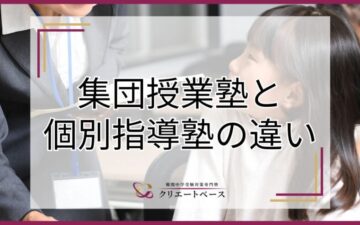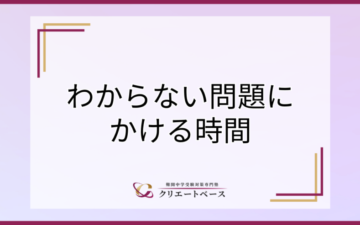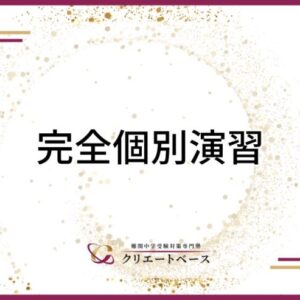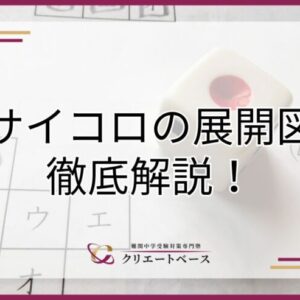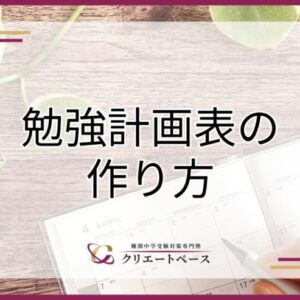今年の関西中学受験は、1月14日が早めの統一入試日。あまり気にかけないように年末年始を過ごしていたものの、そろそろ気になり始めたころですね。
当塾においては、「最大出力の70%をコンスタントに出力することで合格しようね」というスタンスを取っているため、直前期であることを根拠にした特別な対応もありません。これまでよりも休む時間が多めだったりします。
間違っても、意味もなく「平常心」と連呼することにより、直前期であることをアピールし、結果的に子供たちや保護者様の不安を煽り立てるというようなこともありません。
個人的には、3日勉強して3日休んでぐらいのスタンスでもいいと考えてます。一応、直前講習もある程度の演習時間を組み込んではありますが、無理せず取り組んでください。
「無理せず」というのはどの程度なのか?と、子供たちから具体的判断基準の提示を求められそうですが、簡単に言うと「気持ちがのらなくなったら」といった感じです。
過去問も6年の最初あたりからやっているため、「過去問どうしよう」とかいう話題も皆無です。
車の運転と同じで、大阪東京間の500キロを走るにあたり、猛スピードで走って休憩するよりも、時速100キロでコンスタントに5時間走るほうが効率的じゃない?というような具体例だとわかりやすいかもしれません。
中には出力を最大出力の50%以下に落として、演習時間を長時間化するお子様もいらっしゃいましたし、あえて出力を上げて点をとりにいきと色々なパターンも試していたようです。
結局のところ、出力と継続時間というある程度の相関関係があるパラメーターをいじるだけの話なので、それに基づいてアドバイスはしたものの、このあたりも自らで適切なものを見つけられるようになったのは、成長なのでしょう。
自分たちのことです。試行錯誤は最後まで自分で重ねてください。
子供たちは、自らに関与する大人を本当によく見ています。
長年にわたり、常識と言われる概念にさらされ続けてきた大人よりもずっと、素直にそして的確に判断します。
大人の役割は、子供たちに重大な危険が迫っていることを、それまでの経験則により察知し回避させることに尽きるのでしょう。
残されたやるべきことというのは、試験当日、その時にその場にいるだけ。
常日頃から、自らが主体となって判断することを要求され、それに応えてきたのです。目的が何であり、それを遂行するのに適切な手段は何であるかを一瞬で判断するということができるようになった子どもたちには、いともたやすいことだと思います。
本来の自立というものは、上記のようなことを言うのです。
自立した上での学力であり、学力があるが故の自立なのです。
今年は、思いついたことは躊躇なくすべて実行しようと思っています。
よろしくお願いいたします。